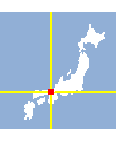日本甲冑 デジタル絵本
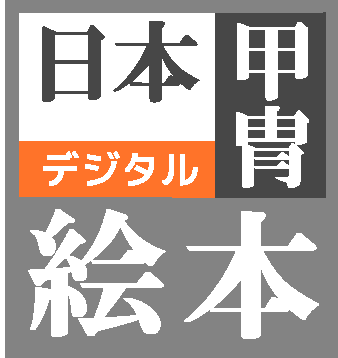

平安後期の華麗な大鎧を原点に、時代背景に応じて変化してきた日本甲冑の16領+番外2領 (甲冑は「領」と数えます) のデジタルイラストと説明のページです。
管理人のことは このページの末尾に記載しています。
平安~鎌倉時代
大鎧
 16
16
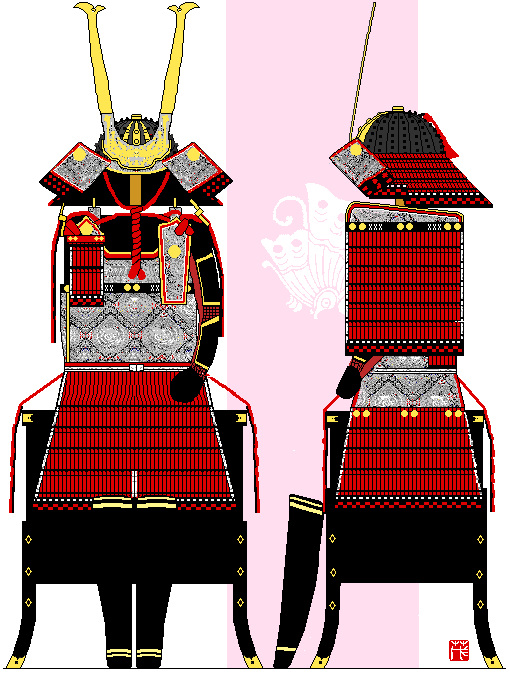
平安時代後期~鎌倉時代につくられた、国風文化を背景とする華麗な古式鎧です。
大鎧は、騎馬/弓矢戦を展開した上級武士が主に着用した鎧で、横に広がった兜の「しころ」や大きな「吹き返し」、盾のように大きい「大袖」、騎馬に適するよう四分割された草摺などが特徴です。
初期 胴丸
 16
16
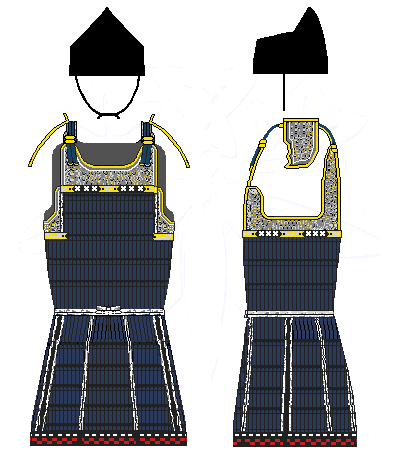
上級武士の騎馬/弓矢戦の一方で、刀や槍などで近接戦を行っていた中級武士の鎧です。
動きやすい樽型の胴や足さばきに配慮して多分割された草摺等、近接戦に適した工夫がなされていました。
切付小札 二枚胴具足
 16
16
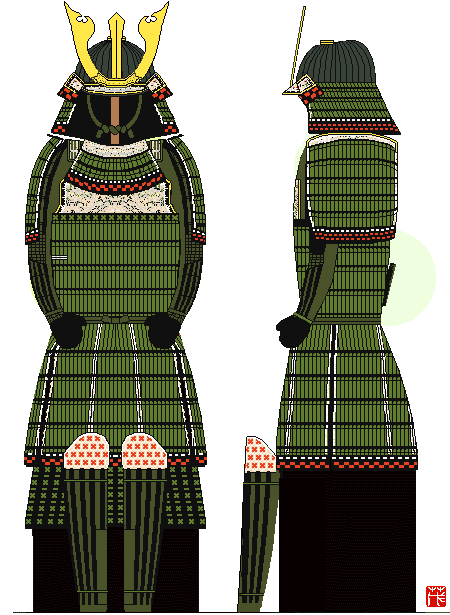
戦さが激しさを増した室町時代末期になると、古式の意匠と生産性の高さをあわせ持った「切付小札」での二枚胴の甲冑が作られ始めました。
武具機能が充実したこれら甲冑は武具の機能を具え足りた「具足」と呼ばれました。
戦国時代
当世具足
 16
16
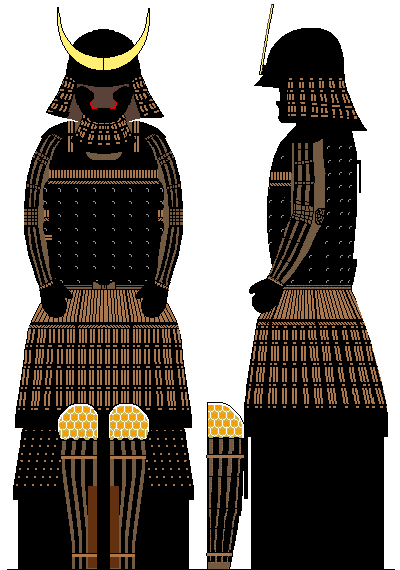
戦国時代、甲冑は武具機能に特化した「戦う道具」へ変化するとともに伝統や様式にとらわれない個性化が進みました。こうした甲冑は「当世具足」と呼ばれました。
また、敵味方を見分ける旗指物(はたさしもの)が常用化し、武士を認知する兜の立物(たてもの)が多様化しました。
以下は、よく知られている戦国武将の特徴ある当世具足です。
伝明智光春 南蛮具足
 16
16
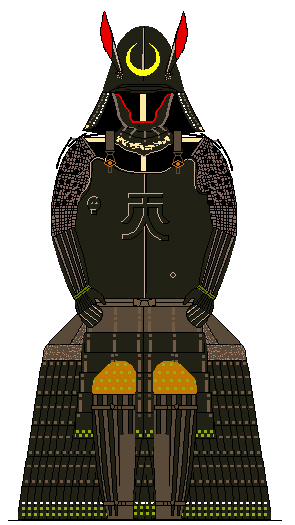
明智光秀の重臣であった明智光春の所用と伝えられる具足です。
兜は前面が二重構造、胴は一枚の厚い鉄板を打ち出した和製南蛮胴です。
伊達政宗 仙台具足
 16
16
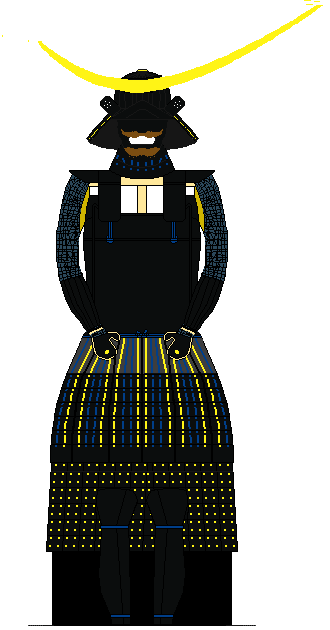
東北の雄 伊達政宗の五枚胴具足です。
強固な鉄の胴に、無用な大袖を小さな鉄板の小鰭(こびれ)に置き換えたこの甲冑は「仙台具足」と呼ばれています。
徳川家康 大黒天具足
 16
16
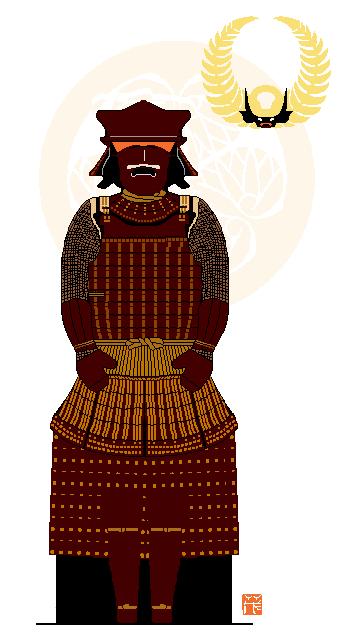
徳川家康が関ヶ原の戦いで着用したとされる実戦甲冑で、特徴的な大黒天頭巾の兜に取り付けられたしころは二重構造となっています。
家康着用の甲冑には前立は装着されていませんが、歯朶(しだ)の前立を装着した奉納鎧の模作が、家康を顕彰する御写形として徳川家代々でつくられてきました。
井伊直政 彦根朱具足
 16
16
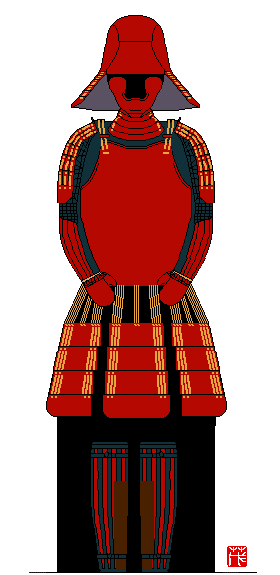
「井伊の赤備え」で知られる彦根藩の初代藩主 井伊直政が関ヶ原合戦で使用したと伝えられる甲冑です。
兜は鉄板を打ち出した頭成兜、胴は簡易二枚胴、籠手は小さな袖が一体化した「毘沙門籠手」の実戦甲冑です。
井伊直政 御召替具足
 16
16
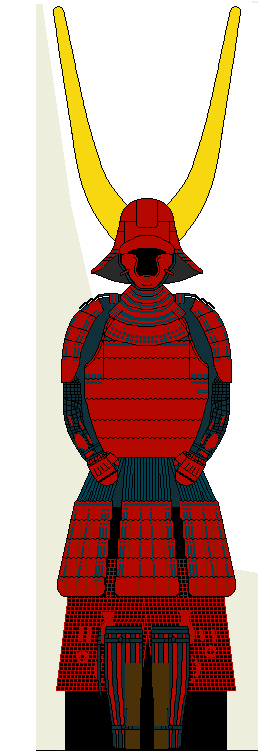
井伊直政の「御召替」具足です。
大天衝脇立を備えたこの甲冑は代々の藩主の甲冑の基本形として継承され、藩主以外がこの大天衝脇立を装着することは許されませんでした。
徳川家光 突杯兜具足
 16
16
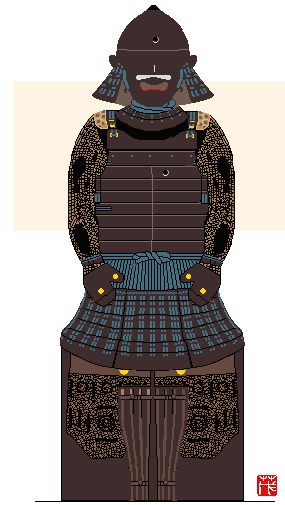
戦国の記憶が残る江戸初期の徳川家第三代将軍 徳川家光の具足です。
簡素で実用に徹した当世具足で、胴に残された火縄銃の試し撃ちの痕から緊張感が伝わります。
この甲冑は、当世具足が行き着いた究極の機能美の甲冑といえます。
江戸後期
井伊直幸 彦根朱具足
 16
16
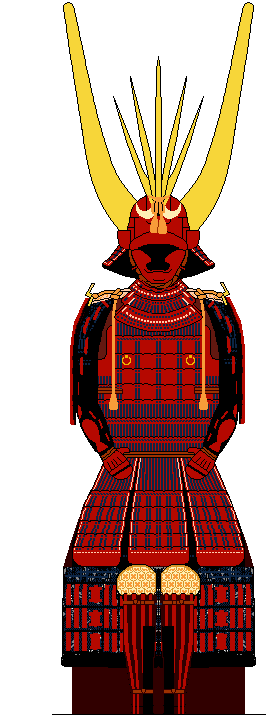
彦根藩八代藩主 井伊直定の甲冑です。
戦さが過去となった江戸中期には、装飾性の高い具足がつくられるようになります。
井伊直弼 彦根朱具足
 16
16
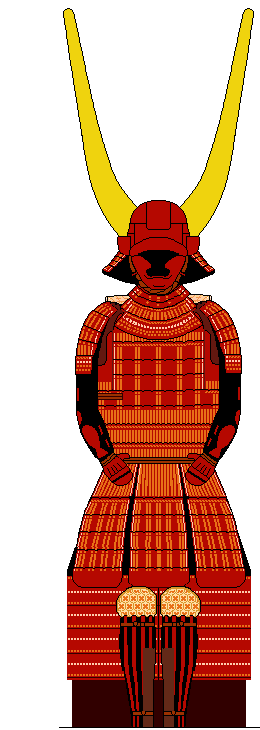
彦根藩十五代藩主であり、江戸幕府大老でもあった井伊直弼の甲冑です。
華美な装飾に陥ることを避け、初代藩主の甲冑へ回帰しようとする意識の伝わる赤備えです。
徳川慶喜 胴丸具足
 16
16
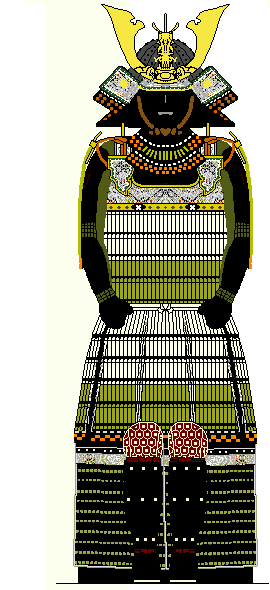
最後の将軍であった徳川家十五代将軍 徳川慶喜が一橋家を相続したときにつくられた古式の胴丸具足です。
後年、フランス式軍隊に倣おうとした慶喜にとって、こうした甲冑の意義は希薄だったかもしれません。
近世~現代
創作甲冑
 16
16
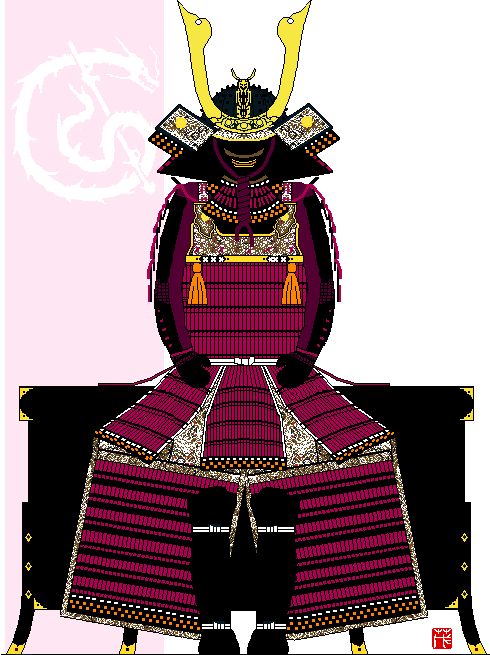
近世、武具として新たに作られことのない甲冑は、武具としての機能が忘れられた鑑賞のための創作甲冑や五月人形へ変化します。
伝天海僧正所用甲冑
 16
16
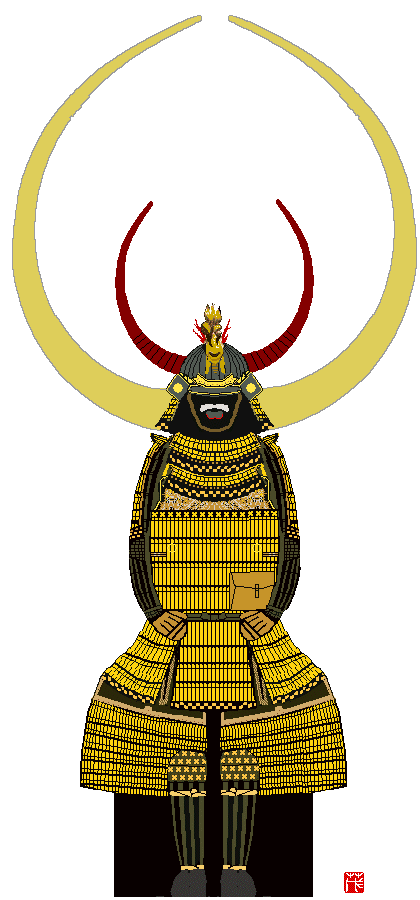
近世の創作甲冑と思われる大阪城所蔵の甲冑です。
明智光秀は死なずして「天海」僧正となって徳川家康を支えたとの伝説がありますが、これが、その天海の甲冑とされています。
なお、この甲冑の前立は、明智光秀が主人公のNKH大河ドラマ「麒麟がくる」の「麒麟」なのが意味深です。
日本甲冑と西欧甲冑
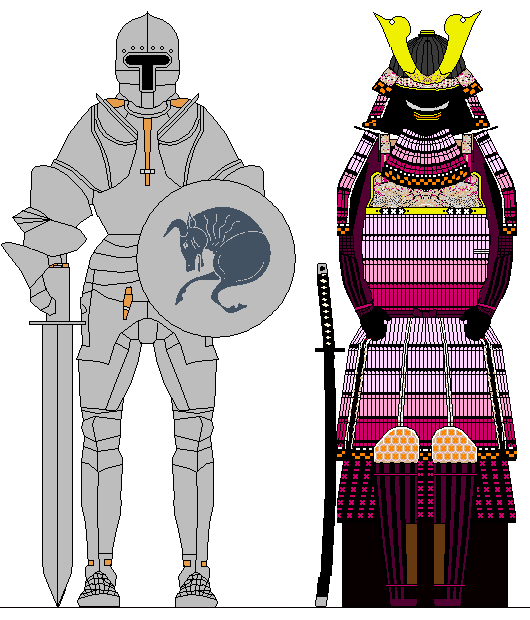
日本甲冑が板部材等をつないだ構造である一方、西欧甲冑はプレートアーマーと呼ばれる鉄板等で全身を覆う構造が特徴です。
この違いは、各々の風土に裏付けられたもので、高温多湿の日本では通風に重きを置いた構造の甲冑が発達し、低温乾燥の気候の西欧では隙間なく身を守る構造の防具が主流となりました。
 ほんまさんのおもちゃ箱へもどる
ほんまさんのおもちゃ箱へもどる
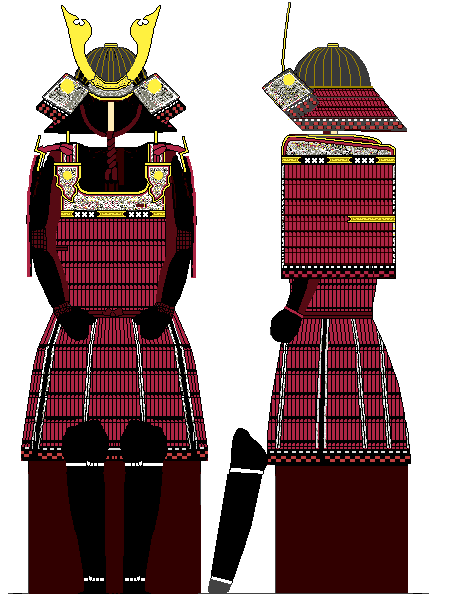
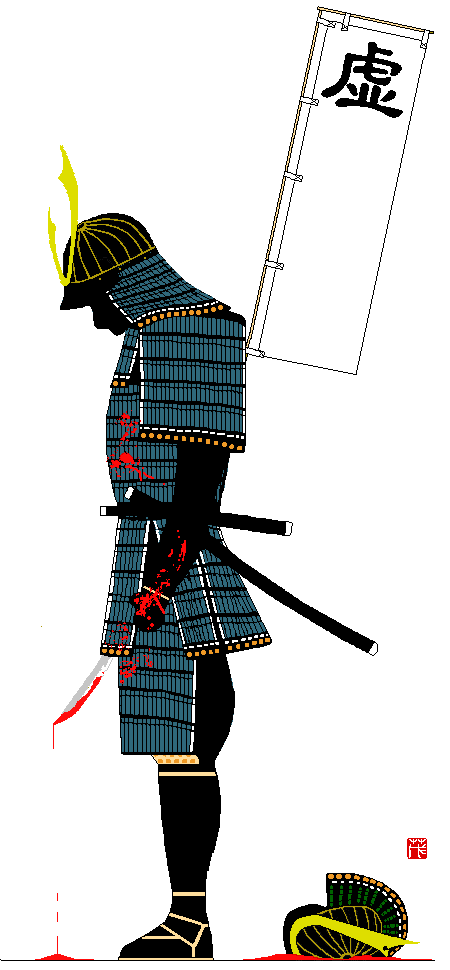

 なまえ 本 間 茂
なまえ 本 間 茂