日本甲冑と西欧甲冑
- 風土と甲冑
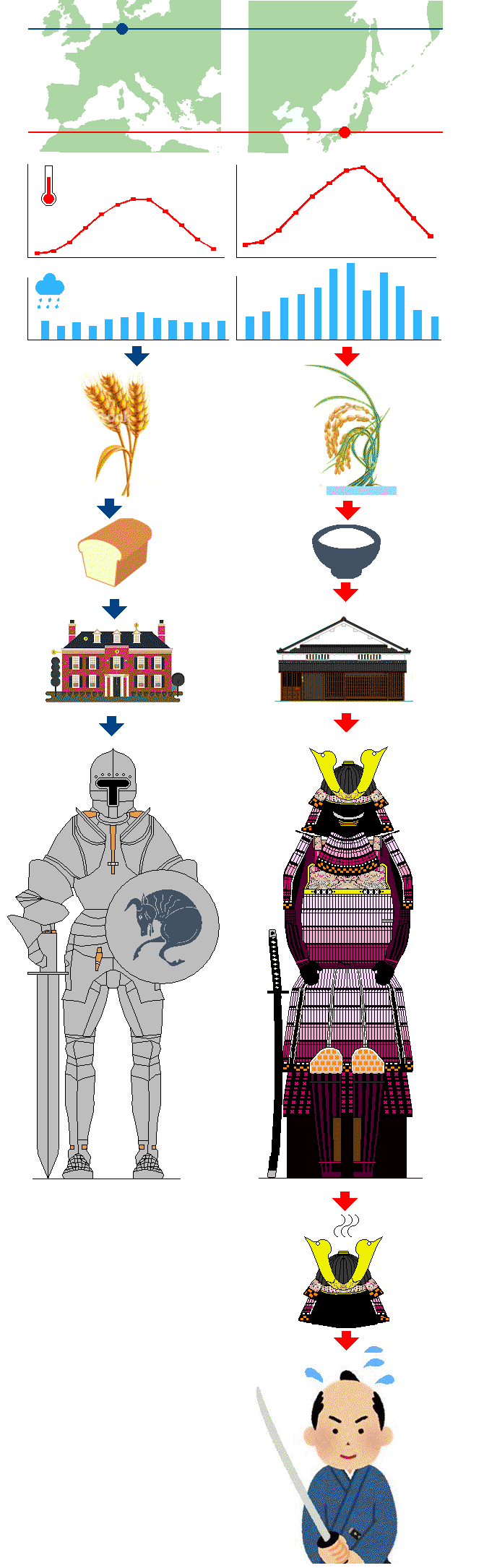
- 日本とドイツ
高い技術力が共通する日本とドイツですが、各々の国の文化の中心を培ってきた京都とベルリンを地図で近づけると、各々の位置の緯度が大きく異なることがわかります。
ベルリンは、日本の北海道よりも北に位置しますが、こうした緯度の差をはじめとするさまざまな要因によって、風土も異なります。
特に、気温と降雨量の相違が大きく、京都の高温多雨とベルリンの低温少雨の相違がグラフからもわかりますが、こうした風土は各々の国の文化の形成にも作用してきました。
- 気候と文化
高温多雨の日本では、たくさんの収量が得られる稲作と米飯の食文化や、豊かな森林資源からの木材を使った建築物が中心となりました。
一方、低温少雨の西欧では、収量の少ない小麦を加工したパン等の食料の不足を肉や乳製品等で補う食生活や、レンガや石で作られた耐寒性のある建築物が主流となりました。
- 華麗な日本甲冑
そして、甲冑など武具も、風土を背景とした構造が求められ、気温が高く、湿度の多い日本では、武具としての防御性とあわせ、戦さによる発汗からの蒸れを軽減するため、板部材を重ねた通気性のある構造の甲冑が考え出されたのです。
そして、春夏秋冬のはっきりした気候によって培かわれた日本人特有の繊細な美意識が、板部材に漆を施して絹で威し、細やかな金工細工を施すことによって華麗な日本甲冑を作りだしました。
- 換気穴
ちなみに、兜の頂部に取り付けられた「八幡座」に空けられた穴は、頭の蒸れを緩和する換気穴で、武士が髷を結い、額の上を剃ったのは、兜をかぶったときの頭部の蒸れを緩和する習慣が大衆にひろがったものなのです。
- プレートアーマー
一方、暑さや湿度への配慮をあまり必要としない西欧では、鉄板で隙間なく全身を覆う構造の「プレートアーマー」と呼ばれる宇宙服のような甲冑が主流となったのです。
- 甲冑から近代兵器へつながる理念
ところで、西欧や日本などで展開された戦さの方法や甲冑の特性などの思考は近代まで根強く残り、参加国の個性が大きく反映された2次世界大戦の戦闘機の仕様や構造等に色濃く表れました。
- 日本
 零式艦上戦闘機21型
零式艦上戦闘機21型
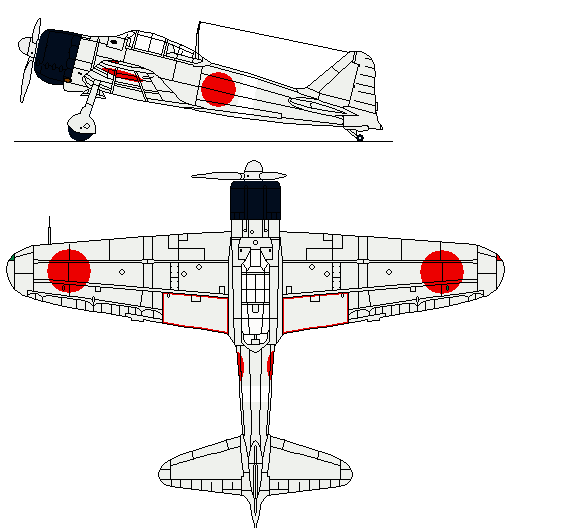
山や丘陵の多い日本の戦国時代の主な戦さは、山城などを「攻め」て、近接で戦う「格闘戦」が多くを占め、使用される甲冑は、日本特有の優雅で繊細な造作でした。
こうした戦さや甲冑の特性を受け継いで設計されたのが零式艦上戦闘機(通称「零戦」)でした。
零戦は「攻める」ための大口径の機関砲を装備し、「格闘戦」で優位に立てる軽量で小型の胴に大面積の大きな翼を備え、その外観は、日本甲冑に通ずる繊細で優雅な姿でした。
ただ、日本の武具には、身を守る「盾」を持つ概念は無かったため、零戦にも「盾」に通ずる防弾板は施されず、悲劇の一端につながることとなりました。
- ドイツ
 メッサーシュミットBf109E
メッサーシュミットBf109E
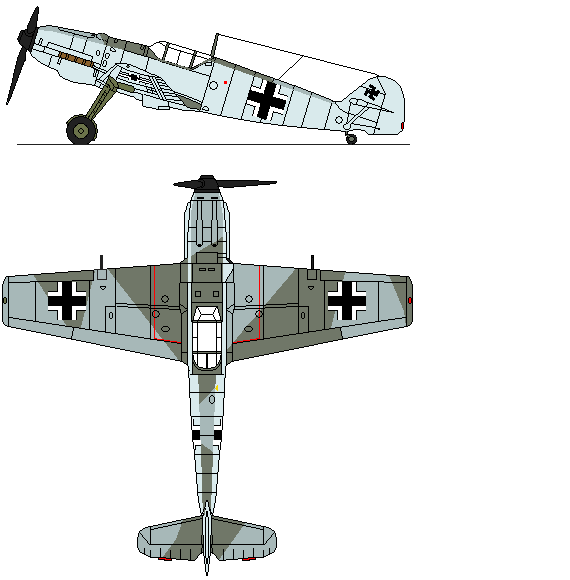
一方、アーマープレートで身を包んだナイト(騎士)が馬に跨り、広い平原で大きな剣と盾を持って正面からぶつかりあう「一撃離脱」が伝統的な戦さであった西欧では、戦闘機の設計も「高速での一撃離脱戦」に重きが置かれました。
そして、日本の同盟国であったドイツの代表的な戦闘機のメーサーシュミットBf109Eはその典型で、空気抵抗の少ない縦長液冷エンジンを搭載したスリムな胴体に小さな翼を備え、敵機に高速で急迫して一撃を加え、速やかに離脱する戦さを展開しました。
また、無駄を削ぎ落とした直線で構成された機能優先の機体は、スリムな西洋甲冑に共通するところですが、操縦席には「盾」に換えて強固な防弾板が装備されました。
- 職人の日本 技術屋のドイツ
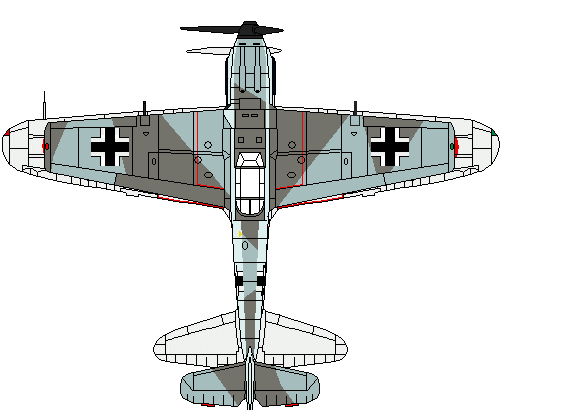
イラストは、日本とドイツの戦闘機を重ね比較したもので、格闘戦を主とするため、短い胴に大きな翼を備えた優雅なデザインに設計された零戦と、高速での一撃離脱戦を主とし、機体が左右の振れることのない長い胴に小さな翼を備えた結果、スリムな機体となったメーサーシュミットBf109Eの対比がわかります。
今日も技術力の高さで知られる日本とドイツですが「職人の日本」「技術屋のドイツ」と形容されるのは、各々の国の風土で育まれた国民性が背景にあったからです。
- アメリカ
 グラマンF6Fヘルキャット
グラマンF6Fヘルキャット
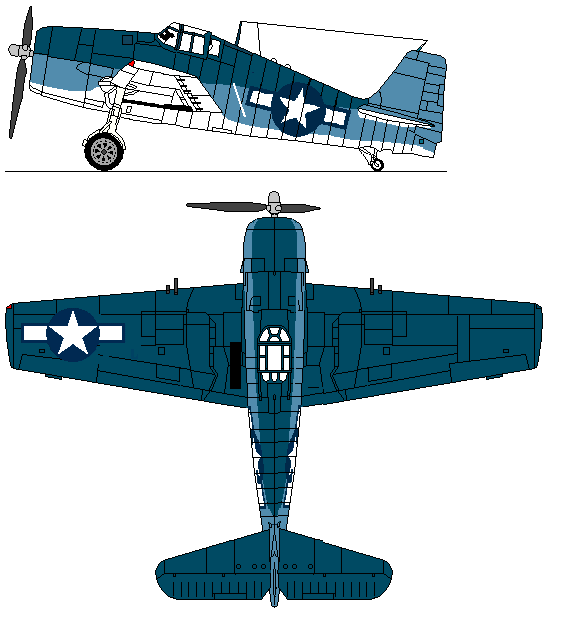
一方、建国から第2次世界大戦までの年月がわずか160年であったアメリカの戦さに対する考えの底流にあったのは「片手に十字架 片手に銃」で、先住民であるインデアンの殺戮を繰り返し、侵奪した土地に牛を飼いながら移動する「カウボーイ」でした。
こうしたアメリカが戦場に送り出した戦闘機は、インデアンから奪った土地からの豊富な資源を背景にした「猛牛」であり、グラマンF6Fヘルキャットがその代表で、格闘戦や一撃離脱などの「技」にとらわれることなく、「力」で敵を圧倒することを主眼としていました。
零戦の倍近い出力の2000馬力級のエンジンで、重厚な装甲を施された大きく無骨な機体を引き回したグラマンF6Fヘルキャットは、アメリカの「力」を象徴する戦闘機でした。
- 「力」のアメリカ
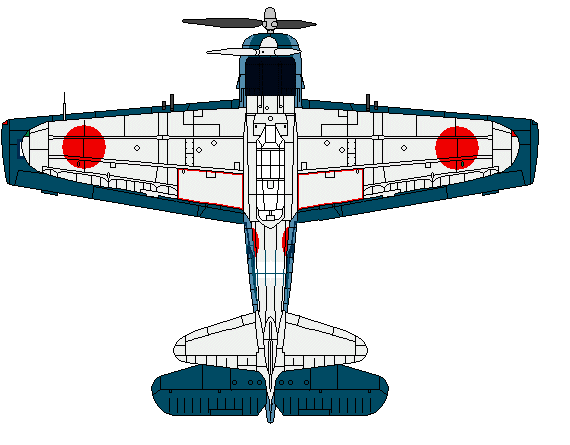
イラストは、零戦とグラマンF6Fヘルキャットを重ねたもので、ヘルキャットの大きさがよくわかります。
「攻め」と「格闘戦」の重きを置いた小型で軽量な零戦には防弾装備がほとんど施されず、わずかな被弾で火を吹き、また繊細なデザインのために生産性が低かった一方、強力なエンジンを搭載した余裕ある大きな機体の「力」のグラマンF6Fヘルキャットは防弾が充実し、無骨ゆえに生産性が高く、戦場での保守点検にも優れており、こうしたアメリカの「力」と「物量」の前に、日本は徐々に劣勢に追い込まれていきました。
- まとめのぐだぐだ話

日本の約12倍の国力を背景としたアメリカの圧倒的な「力」と「物量」に、日本の「優雅と繊細」は徐々に押されて敗戦に至り、その後の日本は「カウボーイ」を英雄視する価値観を下敷きに、グローバリズムの流れと言いながら、実際はアメリカの価値観の「力」と「物量」による「弱肉強食のビジネス」が優先される社会へと移行してきました。
でも、日本の風土に根ざした「優雅さや繊細さ」「やさしさ」は、いまなお、日本の人々の心の底に息づいており、意図せぬ価値観の推移とのギャップが人々に不安を感じさせ、いらだちを覚えさせているような気がします。
甲冑は武具です。人を殺める戦さの道具です。しかし、日本甲冑の「優雅さや繊細さ」にある日本の風土と、この風土で培われてきた文化に目をやると、私たちが忘れたもの、また、不安やいらだちを和らげることのできるものがあるような気がします。
 ホーム
ホーム ホ-ムへもどる
ホ-ムへもどる