麒麟はこない
大河ドラマのネタばらし
 伝天海僧正所用甲冑イラスト
伝天海僧正所用甲冑イラスト
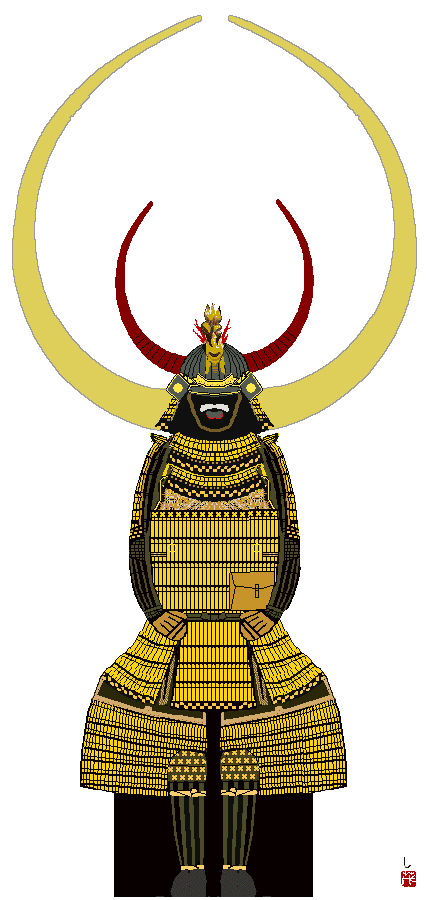
天海僧正
天王山の戦いで敗れた明智光秀は、坂本城へ逃れる途中に武者狩りの手によって絶命したとされています。
ところが、光秀は逃げ延びて徳川家康の側近となり、安定した江戸幕政の基礎づくりに関与した「天海僧正」になったという伝説があります。
麒麟
現大阪城には、その天海が着用したとされる巨大な天衝を装着した甲冑が保管されていますが、この甲冑の兜の前に装着されているのが「麒麟」。
つまり、光秀を主人公とした大河ドラマ「麒麟がくる」の脚本のネタはこの甲冑で、「麒麟がくる」とは「光秀は天海となってやってくる」との意味だったようです。
巨大な天衝
だから、最終回、丹波亀山城で「わが敵は本能寺にある」と告げる光秀の背後にあった巨大な三日月も、この甲冑の天衝と同じイメージ。
大河ドラマ「麒麟がくる」最終回

つまり、敗死したはずの光秀が馬に乗って去っていく最後のシーンは「光秀は死んでいない。いずれ、天海=麒麟となってやってくる。」との暗示だったのです。
だから、いまか いまかと待っていた麒麟は最終回になっても現れず、消化不良みたいな感じが残ったのです。
光秀=天海?
光秀は生き残って天海になったとする言い伝えはあちこちにあり、比叡山の松禅寺には、本能寺の変から33年を経過した「慶長20年2月」に「光秀が寄進した」と刻まれた石灯篭があり、これも光秀説のひとつとされています。
ところが、本能寺の変のときの光秀の年齢を通説の55歳とすると、寄進したときの年齢はなんと88歳で、そのような老齢になってまで石灯篭を寄進する理由が見当たらず、すでに「天海」の身であれば、あえて「光秀」の名で寄進する理由も見当たりません。
つまり「光秀=天海」の説には無理もあり、ドラマでもこうしたことを一切語っていませんが、ドラマに隠された暗号をつないでいくと、その背景に隠された「光秀=麒麟=天海」の構図が見えてきます。
一方、麒麟のヒントになったと思われる大阪城保管の甲冑も、これが江戸時代初期の天海所用の甲冑とすることには疑問の声もあります。
「龍」馬ではなく「竜」馬
ところで、ドラマで光秀がヒーローのようにとりあげられると、一部で、明治維新の立役者として人気のある坂本龍馬は「光秀の子孫」だとまで言われ始めました。
その龍馬を有名にしたのもNHKの大河ドラマ「竜馬がいく」ですが、原作を執筆された司馬遼太郎氏は「小説の人物は『龍』馬でなく『竜』馬という架空の人物で、内容は創作です。」と言っておられ、実際の龍馬は武器商人グラバーに操られていた武器商人だったとの説もあります。
ごちゃまぜ
いろいろな創作が歴史上の真実のようにされ、こうしたことが時代の価値観までもを左右していることが事実ですが、公共放送のNHKの大河ドラマも、史実と空想、真実と虚構がごちゃまぜになった「つくり話」として見なければあかんのですね
イラストは、大阪城に保管されている甲冑を、そんなあれことを考えながらデジタルイラストにしたものです。
 ホーム
ホーム
 ホームへもどる
ホームへもどる