丹波国 亀岡
「丹」は「まごころ」
 亀岡の雲海
亀岡の雲海

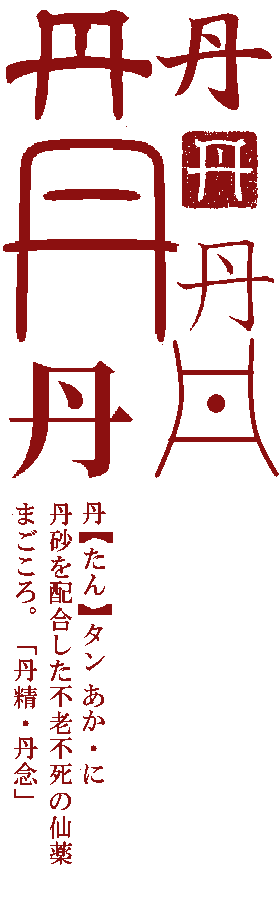
 現丹波標識と丹波小学校
現丹波標識と丹波小学校

霧の海
亀岡は「丹波」です。
冷え込んだ初冬の朝、この丹波/亀岡は深い霧に包まれます。
早朝、のぼる朝日が、この雲海を「丹」(あか)く染めるとき、 そのようすは「丹い波」のようなので「丹波」と呼ばれたとの説があります。
「丹波」
あるいは、太古、亀岡を始めとする盆地地形の丹波地域は大きな湖で、 湖面には、波が削った山肌の「丹」(あか)い「波」が漂っていた遠い記憶から 「丹波」と名付けられたとの言い伝えがあります。
また、豊かな実りのあるところを示す「田庭」(タニワ)が 「タンバ」=「丹波」に変化したとの説や、 赤米の稲穂が風になびく様子が「丹」(あか)い波のようだったところから 「丹波」と呼ばれたとも言われています。
さらには、大蛇に呑まれた武士が、その腹を裂いたとき、 蛇が吐き出した「丹」(あか)い血が湖となったところから 丹波と名付けられたとの伝説もあります。
「まごころ」
一方、「丹」の文字は「丹精」や「丹念」という言葉に用いられるように 「まごころ」との意味がありますが、 この地の名に「丹」の字が用いられたのは、 ここに暮らす人たちのこころを表していたのではないでしょうか。
でも、急ぎすぎた時代のなかで「まごころ」というこころを置き忘れてきたのは、 現在の丹波の人たちも例外ではないような気がします。
言葉さえ忘れてしまったような「まごころ」ですが、 この言葉が意味する「気くばり」「目くばり」「心くばり」を思い出し、 明日へ届けるのも現在の丹波の人たちの役割なのかもしれません。
元丹波
ところが、近年、まちの名に「丹波」を付したことのいざこざや、 わがまちこそ丹波の中心だったとの主張など、 「丹」の意味を置き去りにしたような話題をよく耳にします。
でも、古文書等によると、元祖「丹波」は、
奈良時代に丹波国が丹波と丹後に分割されるまで丹波国であった
日本海近くの丹波国丹波郡丹波郷丹波里丹波村!
(現 京丹後市峰山町丹波)だったそうですよ

 現丹波標識と丹波小学校
現丹波標識と丹波小学校

 ホーム
ホーム

 ホームへもどる
ホームへもどる