丹波国分寺
平安京を育くんだまち
 丹波国分寺イメージイラスト
丹波国分寺イメージイラスト
 イラストは横スクロールできます。
イラストは横スクロールできます。
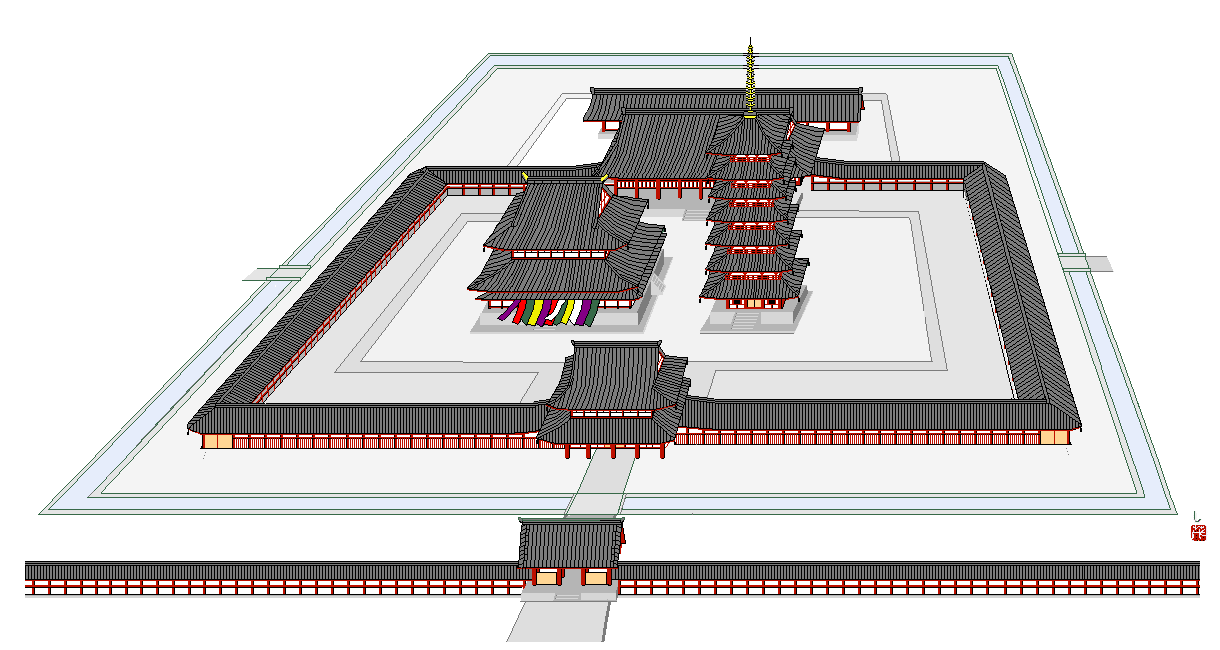
 晩秋の丹波国分寺跡
晩秋の丹波国分寺跡


国分寺
約1300年前、国家の平安と豊かな実りを願い、奈良の大仏で有名な東大寺を総国分寺として全国各地に国分寺が置かれたとき、選ばれた地の多くは盆地であったと言われます。
これは、盆地地形が、敵に対して自然の要塞となるとともに、盆地をとりまく豊かな緑の山林に蓄えられた雨は豊かな緑によってミネラルやカルシュウムを含み、美しい水となって盆地特有の広大な農地に豊かな恵みを与えるとともに、この実りの緑が、また美しい水を守っていく自然の摂理を、当時の人々はすでに知っていたのでしょう。
約束の地
当時の人々は、このことを胸に、国分寺を置くにふさわしい地を求めて全国を歩き、後に平安京が置かれることになる山背国の沼地の向こうの峠をこえたとき、丹波の国で最も美しい水と豊かな実りが約束される丹波/亀岡の地に出会ったのでしょう。
なお、奈良に都があったとき、現在の京都市は、大堰川、賀茂川、高野川が流れ込み、灌木が生い茂る未開の沼地で、奈良の都の「山の背(向こう)」にあるの未開の地であったところから「山背」国と呼ばれていたのです。
平安京の母
約束の地 亀岡に丹波国分寺を置いた当時の人々は、豊かな農地の生産力をさらに高めるために条里制(農地の区画整理)を施して豊穣の地として整えました。
そして、下流に位置する山背国に平安京が置かれるのは、この約60年の後のことですが、豊穣の地として整えられた丹波/亀岡の地の豊かな農産物が、保津川を運河として供給できる母のような存在の立地特性も、平安京遷都の要因のひとつであったことでしょう。
このように、平安京よりも早く開かれ、1200年にわたって平安京の母でありつづけた丹波/亀岡の原点とも言える丹波国分寺の在り日の伽藍をイラストにしました。
 ホーム
ホーム
 ホームへもどる
ホームへもどる